取扱案件
| 相続手続き一覧 ※下記一覧にない場合は相談の際、個別にご確認ください。 | ||||
| 相続開始前 | 遺言書の作成補助 | 遺言者の意思を正確に反映した自筆証書遺言・公正証書遺言等の遺言書の作成を補助します。 | ||
| 任意後見・家族信託 | 依頼者のご家庭事情に合わせ、任意後見契約・家族信託契約の作成を補助します。 | |||
| 遺言執行者の指定 | 遺言者の意思により遺言書の内容を正確かつ迅速に実現します。 | |||
| 相続開始後 | 相続人・遺産の調査 | 遺産分割の前提として、相続人・遺産の範囲を確定する必要があるため、調査いたします。 | ||
| 遺言書がある場合 | 遺言執行者 | 遺言者の意思により遺言書の内容を正確かつ迅速に実現します。 | ||
| 遺産整理受任者 | 相続人全員の意思により遺言書の内容を迅速に実現します。 | |||
| 遺留分侵害額請求訴訟 | 遺言書の内容が特定の相続人の遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額を請求します。 | |||
| 遺言無効確認訴訟 | 遺言の効力に疑義がある場合、遺言の効力そのものを争います。 | |||
| 遺言書がない場合 | 法定相続人が存在しない場合 | 特別縁故者の申立 | 被相続人と特別な関係があった場合(内縁関係、格別な援助をしてきた場合など)、特別縁故者として相続を申し立てる。 | |
| 相続財産清算人の選任申立 | 自己の土地上に被相続人名義の建物が存在する場合、被相続人に債権を有している場合などに相続財産清算人を申し立てる。 | |||
| 法定相続人が存在し、法定相続人間に争いがない場合 | 遺産整理受任者 | 法定相続人間の合意に従い、相続財産を分割する。 | ||
| 遺産分割協議書の作成 | 法定相続人間の合意の内容を遺産分割協議書にまとめる。 | |||
| 法定相続人が存在し、法定相続人間に争いがある場合 | 遺産分割協議 | 特定の法定相続人から依頼を受け、同人の代理人として、遺産分割協議を行う。 | ||
| 遺産分割調停・審判 | 特定の法定相続人から依頼を受け、同人の代理人として、遺産分割協議・審判を行う。 | |||
| 遺産範囲確定訴訟 | 相続人間に遺産の範囲について争いがある場合に遺産の範囲を確定する。 | |||
| マイナス財産の場合 | 相続放棄 | 相続放棄の申立てをする。 | ||
| 限定相続 | 限定相続の申立てをする。 | |||
| 身分関係を争う場合 | 死後認知訴訟 | 被相続人と実親子関係があるのに同人から認知されていない場合に認知請求を求める。 | ||
| 相続放棄、限定相続、死後認知など、期間制限のある手続きは速やかに申し立てる必要がありますし、遺産分割などの期間制限のない手続きにおいても証拠の散逸等の観点からは速やかに申し立てることがより良い結果に繋がります。 | ||||
報酬について
遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| ~300万円 | 11万円~110万円 | 17.6% |
| 300万円~3000万円 | 11%+19.8万円 | |
| 3000万円超 | 6.6%+151.8万円 |
上記は相続事例で最も多い事例である遺産分割に関する代理人業務についての報酬になります。遺言・相続分野については、他にも遺言書の作成補助、遺言執行者、遺産整理受任者等、多岐にわたりますので、具体的には、ご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。
実際の解決事例

相続 特別受益 寄与分 遺産分割 交渉
特別受益と寄与分を認めた遺産分割交渉成功事例
特定の相続人甲に特別受益(生前贈与など)とともに寄与分も認められるような事例でした。そこで、他の相続人らから遺産分割を求められている場合に、甲から妥当な形での遺産分割を行うよう依頼を受け、他の相続人らと粘り強い交渉を重ね、甲及び他の相続人らが納得する形での遺産分割を実現させました。

依頼者が早期解決を求められている場合、とにかく誠実に対応し、相手方の信頼を得ることが必要です。弁護士が入る前の不公平な提案が結果として、事案解決を長期化させてしまうことも少なくありません。
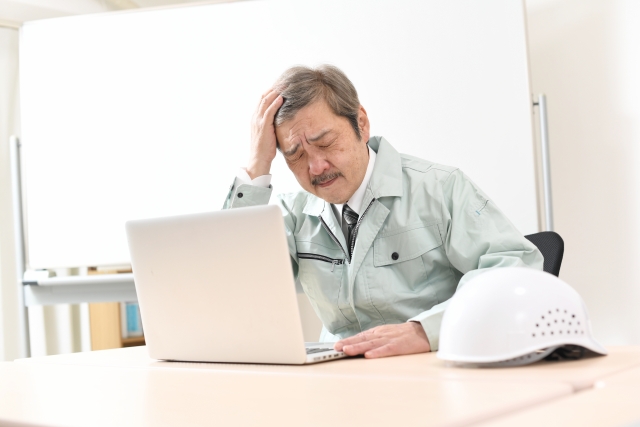
相続 株式 純資産評価 株主 遺産分割
非公開会社株式の相続問題:経営権争いを回避した円満解決
被相続人が非公開会社の株式を保有していましたが、保有株の割合が不明であり、過半数株主か否かで株主兼代表取締役との間で争いのある事案でした。そこで、相続人はいずれも同会社とは無関係であったため、経営権を争わないこととし、保有株の割合が一番多い想定で純資産評価に基づく株式の買取を実現しました。

本事案は、経営権の帰趨に争いはない事案でしたが、やはり非公開株を相手方に買い取ってもらうためには経営権の取得を前面に出して争う必要があります。結論としては非公開株の売却により十分な対価を得ることになりました。

相続 財産分与 DNA鑑定不能 死後認知
死後認知請求に成功した事例:間接証拠を駆使して認知を勝ち取る
被相続人の子が認知されていないため、死後認知を申し立てることになりましたが、戸籍上の兄弟がDNA鑑定に応じず、被相続人の兄弟姉妹は既に死亡しているか、極めて高齢のため、DNA鑑定が難しい事案でした。そこで、時間をかけて間接証拠を収集し、それらの間接証拠を積み上げることにより、裁判所に死後認知請求を認めさせることができました。

死後認知の場合、認知されている親族がDNA鑑定を拒むことはよくありますし、仮にDNA鑑定が実施できたとしても鑑定結果による推定力にはレベル差があります。本事案は丁寧に証拠を収集・提出することで認容させることができました。
ご相談の多い事例 01【相続人間の遺産分割トラブル】
※下記は実際の案件ではありません。実際の案件を基にして、ももとせが得意とする示談をベースにした参考事例です。
ご相談の多い事例 02【遺言書の有効性を巡る争い】
※下記は実際の案件ではありません。実際の案件を基にして、ももとせが得意とする示談をベースにした参考事例です。

